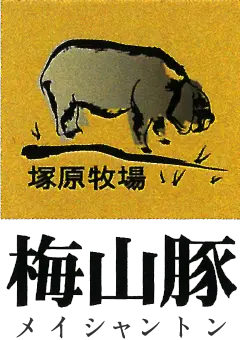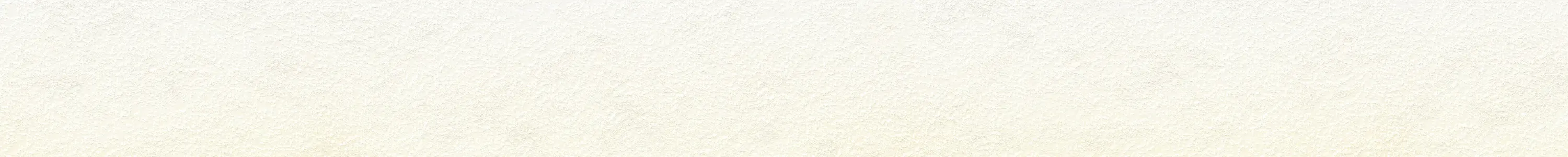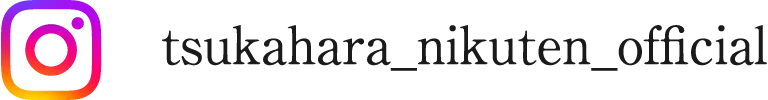飼料倉庫が完成
社長の昇には養豚業の法人化と同時に進めていたもう一つの大きな仕事がありました。それは梅山豚専用の餌工場の建設でした。
養豚業界では、食品工場から食品残渣を引き取り餌にすることはかなり以前から行われていました。振り返れば1990年当時は、パン工場から週2回商品にならないパンを引取ってそのまま梅山豚に食べさせていました。毎回往復160kmも離れたパン工場へ行き手作業で約3トンのパンを積み込む重労働に加え、あんパンから食パンまで様々なパンが混在し栄養価なんて計測しようがありませんでした。
また時々持ち込まれる別の食品残渣を適当に食べさせながら、本当にこのままの育て方でいいのか、という不安を抱く日々を過ごしていました。さらに梅山豚はほとんど売れず経営は厳しくなる一方でした。
珍しいだけでは売れない、本当の意味で求められる豚肉を作らなくてはと決心し、昇は1996年に筑波大学の大学院へ社会人入学し学び直すことにしました。
悪臭や騒音のイメージが強い養豚業がその地域に受け入れられ必要とされる産業になるにはどうすれば良いのか? 梅山豚と昇の羅針盤が動き始めた瞬間でした。
大学院では環境科学を専攻し、パンに限らず様々な飼料原料をピックアップしその栄養価を計測しました。また乾燥して保存することによる環境への影響も調べました。人口が爆発し食料生産が追い付かなくなる時代を迎え、地球を救う豚としてNHKで取り上げられた梅山豚の特徴である「人間と穀物を争わず共生できること」を目指し自ら餌づくりを始めることにしました。休耕田で作る飼料米やトウモロコシ、大麦や小麦などの国産穀物の他、パンの耳や麺類や麦茶粕などのエコフィードの飼料原料を混ぜる比率を変えながら試しました。すると肉質に変化が現れてきたのです。脂の質もあっさり軽くなり、肉汁も増え、肉質は柔らかくなり、美味しいと評判になった梅山豚はファンを増やしていったのです。
農家さんに委託生産をしている飼料米と、自社生産をしているトウモロコシは合計50トンにのぼり、年1回の収穫分を保管しながら1年かけて使う事と、農産物以外のエコフィード原料も保管するためにも100トン収納可能な倉庫が必要となりました。近所に借りていた倉庫では手狭になり、ついに2016年、念願の自社飼料倉庫を建設することになりました。完成した倉庫は梅山豚のためだけに集められた飼料原料で埋め尽くされました。そして昇は思いました。次は本丸飼料工場の建設だと。