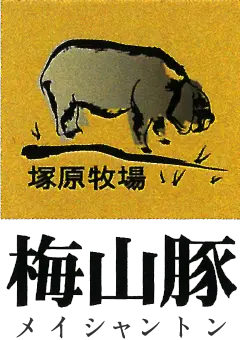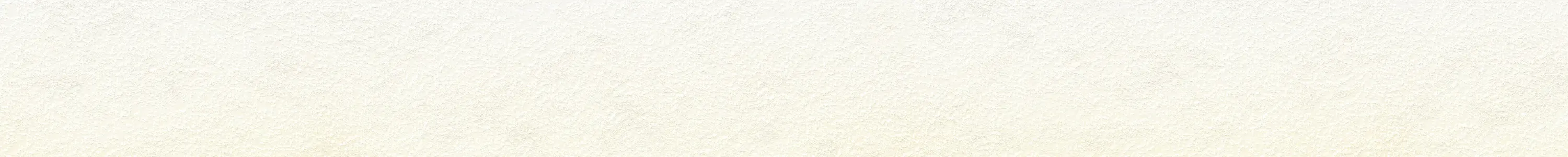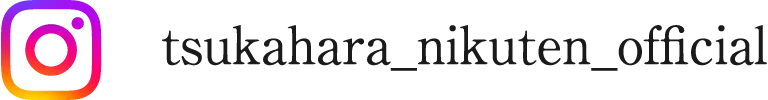農業ファンドからの出資
養豚業の法人化を達成した社長の昇にはその次の目標がありました。それは資本の強化でした。生産規模を拡大する際に多額の設備投資がかかる養豚業、売れない時代が長かった梅山豚は利益の蓄積が少なくどうしても銀行からの借入金に頼る経営になっていました。借り入れをしても低金利であれば経営に及ぼす影響は少なく落ち着いてものづくりに打ち込めます。しかし将来金利が上がることを見越して資本金の強化が必須の課題でした。
そこで考えたのが農業ファンドからの出資でした。前職ベンチャーキャピタルで働きファンドには詳しかった昇ですが24年もの間ファンドとは無縁の仕事をして来ました。しかし時代は農林省が農業ファンドを立ち上げそれに続くように各銀行もこぞって農業ファンドを組成し法人化し経営規模を拡大する農家に向けて出資をしました。農業経営も借入金や補助金に頼らない時代に入ろうとしていました。養豚業の法人化を完了しグループ経営に移行したのも農業ファンドからの出資を考えてのことでした。
先ずは農林省のファンドに打診してみましたが条件が折り合いません。その後複数の取引銀行のファンドとも話を進め遂に2017年12月SMBCアグリファンドからの出資を取り付けました。
それまでは果たして私たちの会社や梅山豚はどのくらいの企業価値があるのか想像もしていませんでしたが、具体的な企業価値がファンドから提示されると梅山豚のブランド価値が非常に高く評価されていました。梅山豚ブランドを基に成長する未来をファンドは描いてくれて、昇は嬉しさとともに期待に応えなくてはならないと身が引き締まる思いでした。
これにより全体の19%の株式をSMBCアグリファンドが保有することになりました。その結果社長の昇の持ち株比率は40%となり過半数を割りました。社長の持ち株比率が過半数以下になると経営権も不安定になりファンドからの出資について疑問視する株主もいました。そんな株主を根気よく説得してまで資本の強化を図りたかった社長の昇でしたが後にこの資本の強化は思わぬ形で経営に影響を及ぼすこととなります。しかしこの時はまだこれから起きる試練については誰も知る由もありません。私たちに訪れるであろう明るい未来を想像しそれに向けてチャレンジすることだけを考えていたのです。